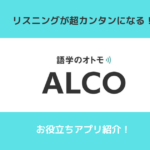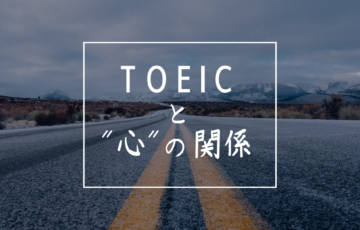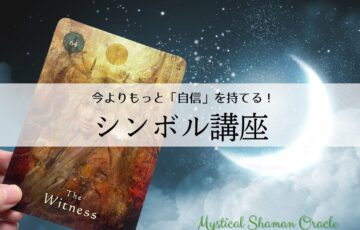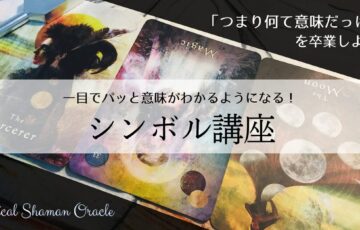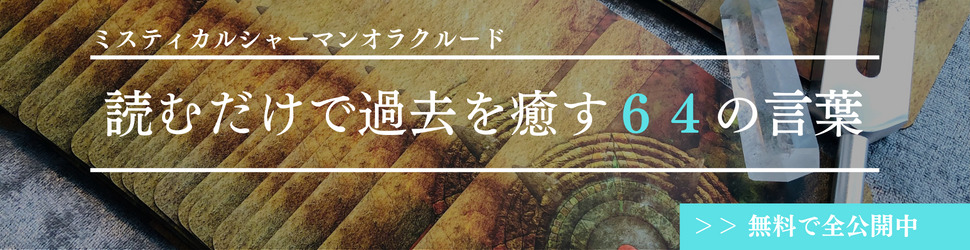第二言語習得研究の第一人者、スティーブン・クラッシェンという言語学者が提唱した仮説の中に、「情意フィルター仮説」というものがあります。
情意フィルターとはつまり、
一言で言えば「心のハードル」のことです。
第二言語を習得するにあたり、インプットやアウトプットなどの具体的なトレーニング云々は別として、「言語に対して心が開かれていることが重要だ」と仮説を立てたのですね。
今日はこの「情意フィルター仮説」について説明してみたいと思います!
情意フィルターについて
情意フィルター仮説とは、学習者の心理的(感情的)な状態が言語習得に影響を与えているというものです。
「動機付け」「自信」「不安」の3つの要素について、ポジティブならば言語習得は上手くいき、ネガティブなら難しくなるという仮説です。
情意フィルターが低い状態
→ 動機がハッキリしていて、自分に自信があり、不安があまりない情意フィルターが高い状態
→ 言語を学ぶ動機がなく、習得できる自信がなく、「失敗したらどうしよう」等の不安が強い
心理状態が良い=フィルターが低い
心理状態が悪い=フィルターが高い
と言うこともできますね。
このフィルターが低い(心理状態が良い)状態の時は言語が習得しやすく、逆にフィルターが高い(心理状態が悪い)状態の時には、どんなに効果的なトレーニングをしても、習得が難しくなってしまう傾向がある、ということです。
動機付け、自信、不安。
この3つの要素と向き合ってオープンな状態を保ち、情意フィルターを低くしておくことが、言語習得の鍵なのです。
情意フィルター仮説の限界
クラッシェンの情意フィルター仮説については、心理面が言語習得に影響するという点に幅広い同意が得られています(私もめっちゃ賛同しています)。
しかし「動機付け」「自信」「不安」の要素を細かく見ていくと、学習者にはたくさんの例があって一概には言えず、それが情意フィルター仮説を万能とできない一因になっているのです。
「間違う不安が強いからこそ勉強に励み言語を習得した」という人がいた場合、クラッシェンが提唱した「不安が強いと習得が遅れる」には当てはまらない、と言える。
さらに個人の「言語適性」もあります。
などなど、学習者それぞれの状態は千差万別。だからこそ情意フィルター仮説の一般化は難しく、「結局は学習者それぞれがどう言語に向き合うかだよね」ということになっていきます。
日本人の情意フィルターは高い!
情意フィルターが低い状態
→ 動機がハッキリしていて、自分に自信があり、不安があまりない
情意フィルターが高い状態
→ 言語を学ぶ動機がなく、習得できる自信がなく、「失敗したらどうしよう」等の不安が強い
この基準で考えた時、私たち日本人の情意フィルターはめっちゃ高いといえます。
英語に関してはよくジャッジされたりしますよね。「留学してた割に大したことないな」とか、「発音が悪い」とか、逆に「ネイティブ発音ムカつく」とか。そりゃー話せなくなって当然ですね。
この情意フィルターが低い=話すことに抵抗がない人の英語ってすごいんですよ。片言でも気にせずガンガン喋ってコミュニケーションを取るんです。
私も以前友達とパーティーに行った時、友達がネイティブに「ジス!トライ!グッド!」と言って料理を勧めるのを見て、本当にものすごい衝撃を受けたことがあります。
あんな風になれたら楽しいだろうなと思うけれど、自分で情意フィルターを下げるって難しいですよね。持って生まれた気質も関係するし、色んな経験の中で固定化されてしまうものだからです。
情意フィルターを下げるコツ!
でも実は情意フィルターを下げる方法があるんです。
①酔っ払う
まず1つは飲酒!笑
お酒を飲めば情意フィルターが下がります。
「バーに行くとなんか英語がスラスラ出てくる気がする〜!」とよく言われますよね。これはお酒を飲むと警戒心が薄れるからです。楽しくなったらいいんです。
②セラピーを受ける
「動機」「自信」「不安」の3つが良い状態になれば良いので、心理カウンセリングや心理セラピーなどのセッションを受けて「私は私でオールオッケー!」な状態を作り出すと、フィルターは下がります。
実際私はこれで大幅に英語を楽に話せるようになりました!
③英語を承認されまくる
日本の英語教育は「減点方式」ですけど、それって本当に情意フィルターを爆上げしてるなって個人的には思います。
他人から「あなたの英語いいよー!」って言ってもらえて、ちょっとずつ自分でも「確かにいいかもー」って思えたら、フィルターも少しずつ下がるでしょう。
海外の友達を作るとか、
褒めるタイプのコーチを探すとか、
承認してくれる人を探しましょう。
まとめ

クラッシェンの「情意フィルター仮説」いかがでしたか?単純に言えば「心理状態が良ければ第二言語の習得が早まる」ということで、ある意味すごーく普通のことなんですよね。
*参照サイト:http://www.sdkrashen.com/content/books/principles_and_practice.pdf
今までの日本の英語業界では、「英語くらい喋れたらいいよね!」みたいな不安や欠乏感を煽るやり方が多くありました。
でもそんな時代はもう終わり。
もっともっと自分らしく、
もっともっと楽しく、
英語を自己表現の手段として使う時代になります。
あなたも自分の「情意フィルター」について考えてみてくださいね!
*外山周の「英語リーディング」はこちら!
https://colorflow.jp/english-reading/