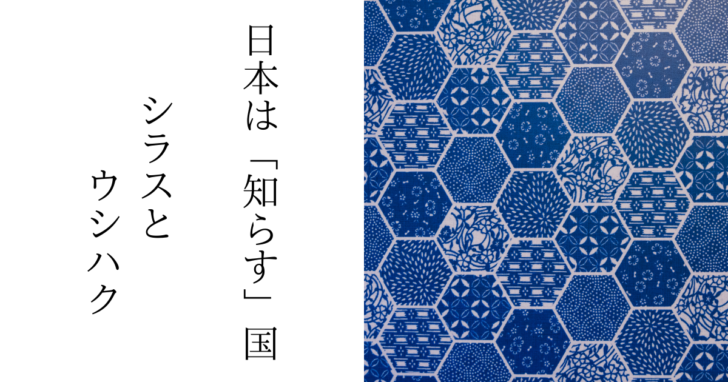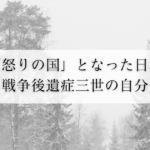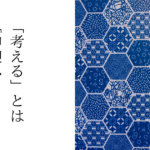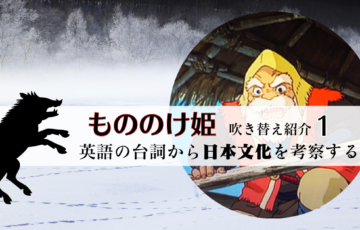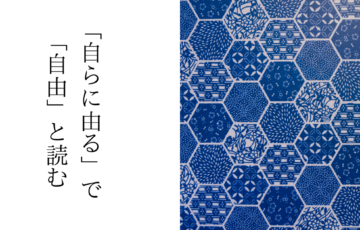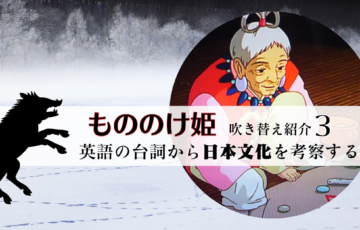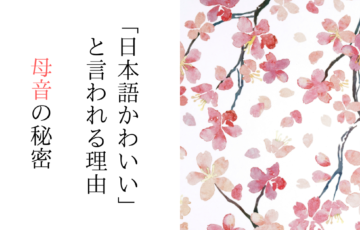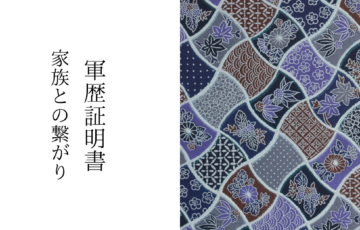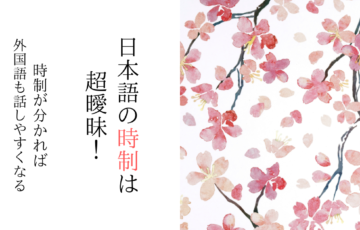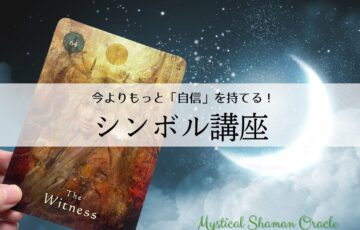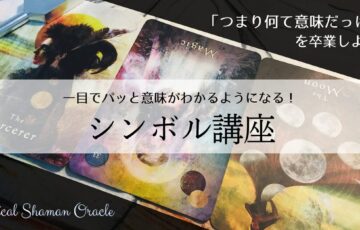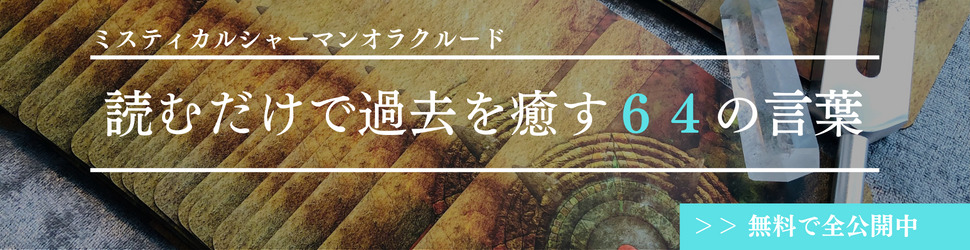日本は「知らす国」。
この「知らす」という言葉を、聞いたことがあるでしょうか。
日本が「知らす国」であること、そして日本の古い神話や祝詞に出てくる「シラスとウシハク」という言葉は、日本が世界に誇れる概念です。
現代の日本人は、「知らす」という言葉を知らない人が多いかもしれません。
社会が大きく変わろうとしている今だからこそ、「知らす」と「うしはく」という言葉を知っていきましょう!
こんな情勢ですが、ちょっと心が楽になるかもしれません。
シラスとウシハクの意味
まず、ざっくり意味を確認してみます。
・知らす(シラス)
→ 知る / 一体化する
・主人(ウシ)履く(ハク)
→ 所有する
反対の意味であることが分かりますね。
日本ではずっと昔の時代の神話「古事記」によって、既に「知らす」が良しとされ、「うしはく」はだめですよとされていました。
それぞれの意味をもう少し詳しくみてみましょう!
知らす = 一体化する
「知らす」は、神道の祝詞の一節に出てくる単語です。
「瑞穂の国を安国とたいらけく知ろし食せ」
これは「安寧な国となるよう国を知り食しなさい」という意味ですね。
「国を知り食べる」。
これはつまり、「国と一体化しなさい」ということです。
もともと日本語の「知る」には、「一体化する」という意味がありました。英語の「know」との違いがここにあります。
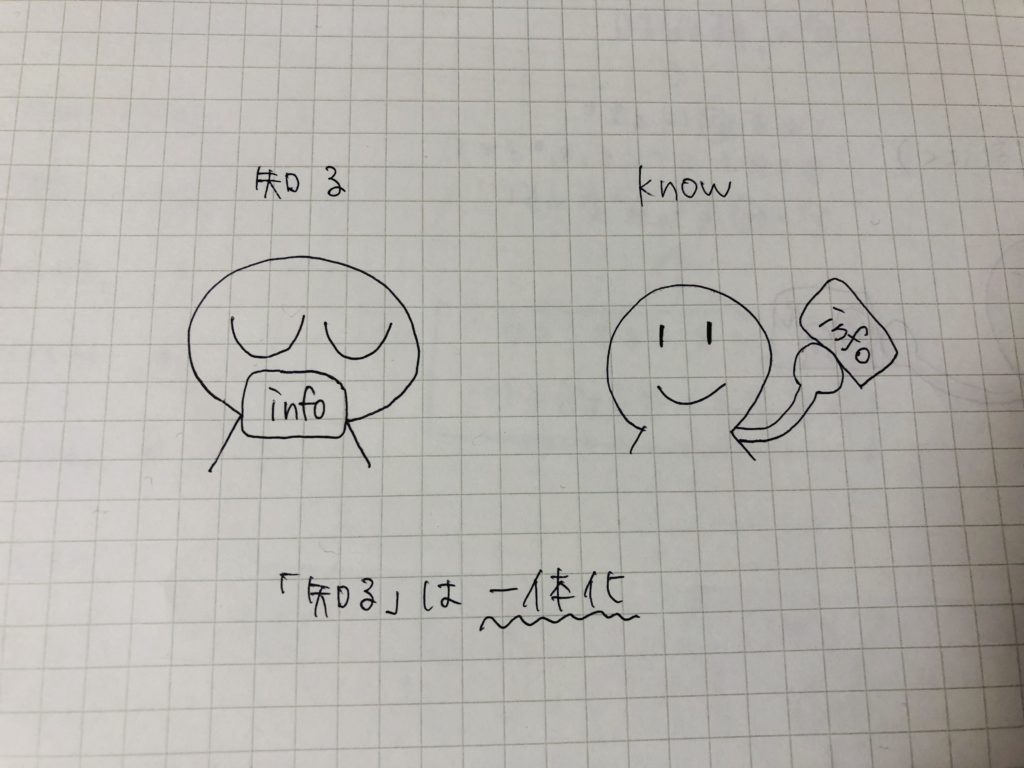
ただ知識として知るのではなく、
一体化することが「知る」こと。
古事記に出てくる天皇陛下の遠いご先祖様とされる神さまは、「国と一体化すること」を説かれていたのです。
身分の差なく一体化する国、
国民を「おおみたから」とする国。
自分を愛するように国民を愛し、
国民もまた自身を大切にするように国を大切にする。
そんな国こそが「知らす国」。
日本の原形が「知らす」にあります。
うしはく = 所有する
一方のうしはくは、「主人履く」と書きます。
主人が履く(所有する)訳で、一体化するわけではありません。
自分の好きに扱って良いものとして所有するので、酷い扱いをしようと、利用するだけして捨てようと、それは所有者の自由であると見なされます。
昔の大陸で行われていたのは、この「うしはく」の統治であったと言えるでしょう。
王が国と国民を所有物と見なし、私的に支配し贅沢の限りを尽くし、最後に反乱によって倒れ、力によって新たな王が立ちます。
そして争いと「所有」が繰り返されていたのですね。
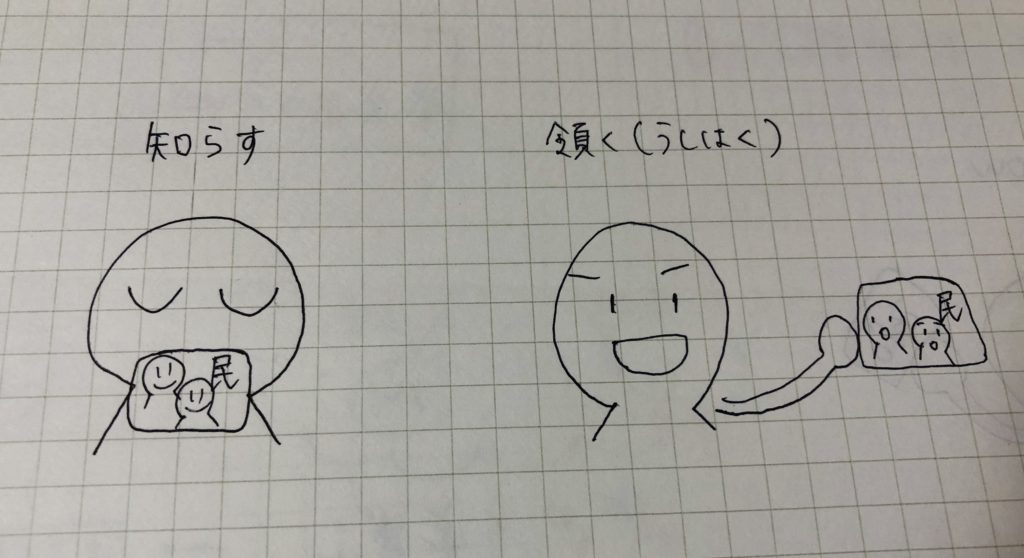
日本は知らす国
日本でははるか昔、古事記の「国譲り神話」によって、すでにこの「うしはく」が否定されていました。
「国譲り神話」と言うと、「あー国を無理やり取られた話でしょ?」と思われがちですがそうではありません。
大国主神が「うしはく」で民を統治した
↓
国は経済的に栄えた
↓
でも「栄えればいいってもんじゃない」と否定
↓
天孫を遣わして国を明け渡すよう告げた
これが国譲り神話の背景だと言われます。
どんなに国が経済的に栄えても、「うしはく」はだめ。
「知らす国」であることの大切さを説いたのですね。
これからの時代の「知らす」と「うしはく」
日本では1300年前(!)からあった、「知らす」と「うしはく」の概念。
今は日本でも「うしはく」が強い力を持っていますが、きっとこれからどんどん、「知らす」が主流になっていくでしょう。
日本が真の「知らす」を取り戻す時代になったのです。
もう一度手書きメモを見てください。
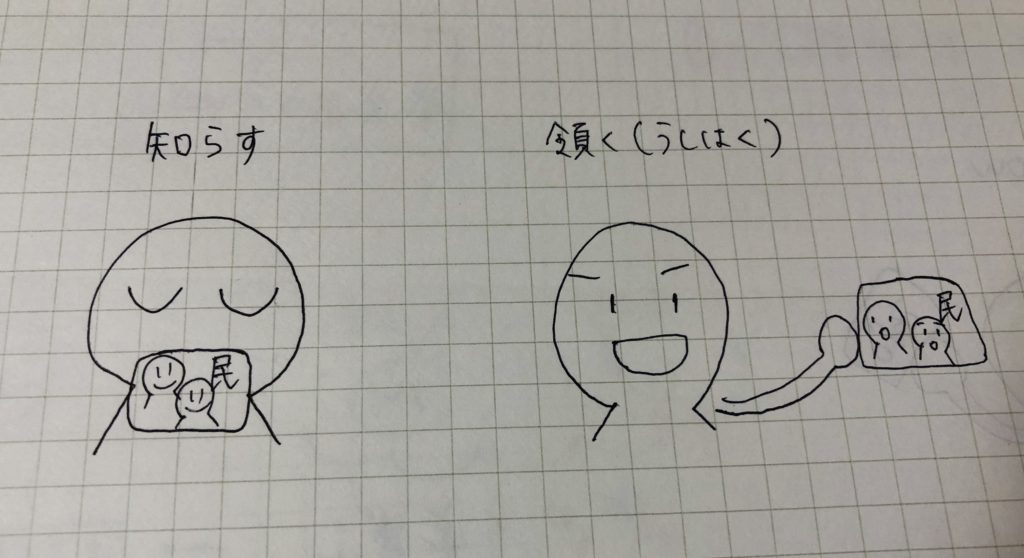
「うしはく」は「分離」ですよね。
分離しているからこその「所有」です。
その背景にあるのは「恐怖」です。
恐怖があるから、人は「所有」をしたくなるのです。
昔の大陸の王様も、きっと民衆の力が怖かった。
怖いから力で所有し、虐げて力を奪わなくてはいけません。
常に叛逆の危険もあって、怖かったのです。
一方の「知らす国」だった日本は、
あの戦後の混乱の最中、
昭和天皇がご自身の足で全国行脚を行い、
民の中に入っていくような国でした。
昭和天皇は、なぜそれができたのでしょうか。

日本人が「知らす」を知っていたら、コロナウイルスの時のマスクの買い占めや転売も、こんなに大きくは起きなかったことでしょう。
昭和天皇は、全てを承知で丸腰で民に身を晒しました。
たとえ怖くても、それを受容する。
「何が起きても(例え死んでも)大丈夫」と思えたら、
安心感に包まれ生きることができるのです。
日本の長屋的な助け合いも、元々はここに根付いているんですね。
私たち日本人は、経済的な豊かさと引き換えに、
あまりに多くのことを失ってきました。
「うしはく」の会社で苦労しておられる方、
家族や友人が「うしはく」で悩んでいる方も、
たくさんいるでしょう。
もしあなたがそれに苦しんだり悩んだりするならば、
あなたは間違いなく、
「知らす」の魂を持った人です。
「知らす」は一体化し、共有すること。
自分らしく力を発揮し、
人とその力を共有し、
みんなで幸せに生きていく。
そんな「知らす」を取り戻す日本になったら、
どれだけ多くの人が笑顔になるでしょうか。
気付いた人から、戻りましょう。
「うしはく」から「知らす」へ。
「知らす世界」は、すぐそこです。
こんな時代だからこそ、「知らす」を取り戻していきませんか。
関連記事